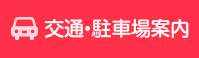院内登録化学療法レジメン一覧
敦賀医療センター 全科レジメン一覧 (2024年3月現在) [PDF形式]
レジメン内容等に関するご質問・お問い合わせはこちらまでお願いします。
TEL:0770-25-1600(代表) 薬剤部レジメン担当者まで
退院時薬剤情報連携加算について
当院では、退院されました患者さんを介して、かかりつけ薬局の薬剤師の方に向けて、「薬剤管理サマリー」の交付を開始しております。
当該サマリーに関し、かかりつけ薬局から伝達したい事項等がありましたら、ご返信ください。よろしくお願いいたします。
一般名処方について
院外処方箋の記載の中で、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(一般名処方)に変更しています。
一般名処方は医薬品名の前に【般】が表示されます。
FAX・郵送等による当センターへの商品名の情報フィードバックは不要とします。
後発品への変更調剤後の報告方法について
後発医薬品への変更調剤時は、必ず服薬指導を行った上でお薬手帳に調剤内容(医薬品銘柄、剤形、規格、用法用量、日数、その他必要事項)を記載して下さい。
FAX・郵送等による当センターへの情報フィードバックは不要とします。 (フィードバックされても次回処方箋への反映はいたしませんのでご了承下さい)
院外処方箋疑義照会事前合意プロトコルについて
当院では院外処方箋における形式的な問い合わせを減らし、患者への薬学的ケアの充実を図るとともに、当院勤務医及び保険薬剤師の照会業務負担を軽減することを目的として、「疑義照会事前合意プロトコル」の運用を開始しております。
本プロトコルの運用にあたっては、プロトコルの主旨や各項目の詳細について十分に理解したうえで、貴保険薬局と当院との間で合意書を取り交わすことを必要条件としています。合意締結の詳細につきましては以下をご参照お願いします。
◆合意締結までの流れ
保険薬局代表者より当院薬剤部<宛先:医薬品情報室400-yakuzai-di@mail.hosp.go.jp>へ以下の必要事項を本文に記入した上で、メールにて連絡(メールの件名は『敦賀医療センター院外PBPM合意締結希望』と記載お願いします。)
【連絡時記載事項】
・薬局名
・代表者名
・所在地
・電話番号
・メールアドレス
↓
当院薬剤部よりプロトコル内容と動画視聴にかかるパスワードをメールにて返信
↓
『院外処方箋疑義照会事前合意プロトコル第2版』 の内容について確認した上で、
『院外処方箋疑義照会事前合意プロトコル説明動画』 視聴
↓
内容について十分に理解したうえで動画内にて提示されるパスワードをもとに、
『院外処方箋疑義照会事前合意プロトコル合意書』を確認。
合意書に必要事項を記入した上で、返信用封筒を同封し当院薬剤部へ送付
(合意書の後ろについているアンケートについてもご協力いただけますと幸いです。)
送付先:
〒914-0195
福井県敦賀市桜ヶ丘町33番1号
独立行政法人 国立病院機構 敦賀医療センター 薬剤部
↓
当院薬剤部にて合意書の内容について確認した上で、合意書に署名し保険薬局へ返信。
↓
以上をもって院外処方せん疑義照会事前合意プロトコルに合意締結となる。
合意締結後、疑義照会事前合意プロトコルに基づく変更調剤の報告については、以下の用紙にご記入の上、当院薬剤部までFAX送信お願いいたします。(閲覧パスワードは合意締結時に合意書の最下部に記載)
『疑義照会事前合意プロトコルに基づく変更調剤報告用紙』
送付先:独立行政法人 国立病院機構 敦賀医療センター 薬剤部
FAX番号:0770-25-7409
院外処方せん疑義照会事前合意プロトコル内容等に関するご質問・お問い合わせはこちらまでお願いします。
TEL:0770-25-1600(代表) 薬剤部
トレーシングレポート・入院時情報共有シート
当センターでは、患者様へ質の高い医療を提供するため、地域連携を強化し【連携充実加算】を算定しており、調剤薬局において【特定薬剤管理指導加算2】の算定が可能です。調剤薬局において電話等により服薬状況や副作用の有無等について聴取した情報をトレーシングレポートでFAX送付をお願いいたします。 内容を確認させていただき、主治医と情報共有し診療に活用させていただきます。
医薬品採用情報
当院薬事委員会の審議結果については、以下の開催月をクリックしてください。
使用開始は原則として委員会開催翌月の1日からです。